社会科「養殖漁業と栽培漁業」の違いとそれぞれの特徴です。日本の漁業は、とる漁業から育てる漁業へとシフトしています。そのあたりは、入試やテストでも出題されるとことです。その代表が、養殖漁業と栽培漁業です。それでは、社会科「養殖漁業と栽培漁業」の違いとそれぞれの特徴をみていきます。
養殖漁業と栽培漁業
| 漁業 | 養殖漁業 | 栽培漁業 |
|---|---|---|
| 特徴 | ずっと人が育てる | 最初だけ人が育てる |
養殖漁業
出荷サイズになるまでを水槽やいけすで育てます。すなわち、魚の子供の頃から大人になるまで、人の管理下で育てられています。養殖漁業は魚を水槽などで育て、放流はしない。
栽培漁業
卵から稚魚になるまでの一番弱い期間を人間が手をかして守り育て、無事に外敵から身を守ることができるようになったら、その魚介類が成長するのに適した海に放流し、自然の海で成長したものを漁獲することです。
その他の漁業
日本近海は、世界の三大漁場の1つにあげられる北太平洋西岸漁場に属し、水産資源が豊富です。とくに東シナ海 やオホーツク海はプランクトンが豊富な大陸棚が広く、また太平洋側には寒流と暖流が出合う潮目があり、よい漁場になっています。
- 沿岸漁業…自分たちが住んでいる町のすぐ目の前の沖で漁をするので、その土地ならではの魚を獲ります。
- 沖合漁業…日本近海の2~3日で帰れる範囲の海が漁場で、20~150トンくらいの漁船を使い、まき網漁などで魚をとります。漁獲量では、日本の漁業の中で沖合漁業の占める割合は高く、約4割を占めています。
- 遠洋漁業…赤道直下の南太平洋や南アフリカ沖など世界の海が漁場です。しかし近年、各国が漁業のできる海域を制限(200海里漁業水域)しているため、日本の船が自由に魚をとることが難しくなり、漁獲量は減っています。
漁業の種類練習問題
次のア~オの漁業の名称を答えなさい。
(ア )漁業…海岸近くの海で行う漁業。
(イ )漁業…日帰りから数日かけて沖合いで行う漁業。
(ウ )漁業…数ヶ月にわたって日本から離れた海で行う漁業。
(エ )漁業…人工的に魚を育てて,出荷する漁業。
(オ )漁業…卵からふ化させた稚魚をある程度まで育て,川や海に放流してからとる漁業。
漁業の種類練習問題解答
ア沿岸
イ沖合
ウ遠洋
エ養殖
オ栽培
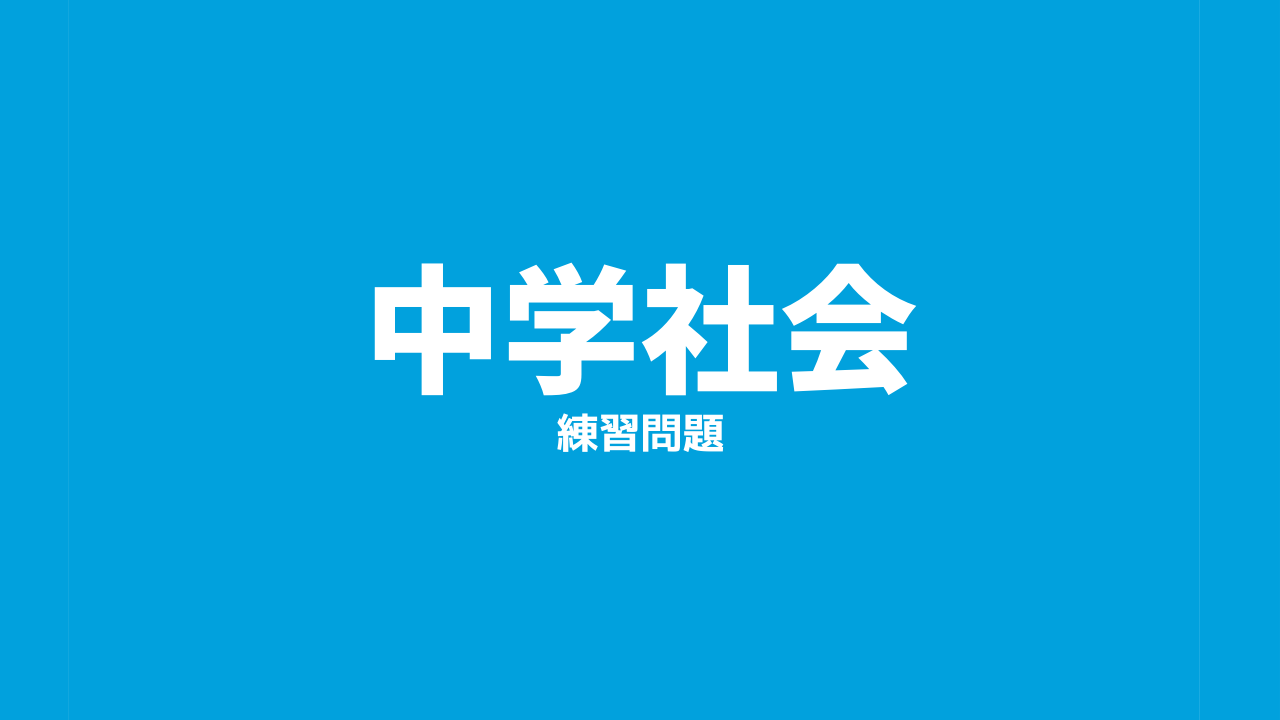

コメント