消費生活の単元は、日常のニュース記事と絡めて出題もしやすくよく問われるのできちんと覚えておきましょう。それでは、中学公民のテストに出る消費者保護の法律についてみていきましょう。
➊クレジットカードの利点は、手元に現金がなくても買い物ができるということである。一方でデメリットは、後日カード会社に代金分のお金を支払うので、計画的な利用が不可欠。
➋消費者の4つの権利は、アメリカ合衆国のケネディ大統領が1962年に発表したものである。日本では1968年に消費者保護基本法(現在の名称は2004年に改正され、消費者基本法)が制定された。
➌クーリング・オフは、特定商取引法や割賦販売法などに定められた制度である。
消費生活
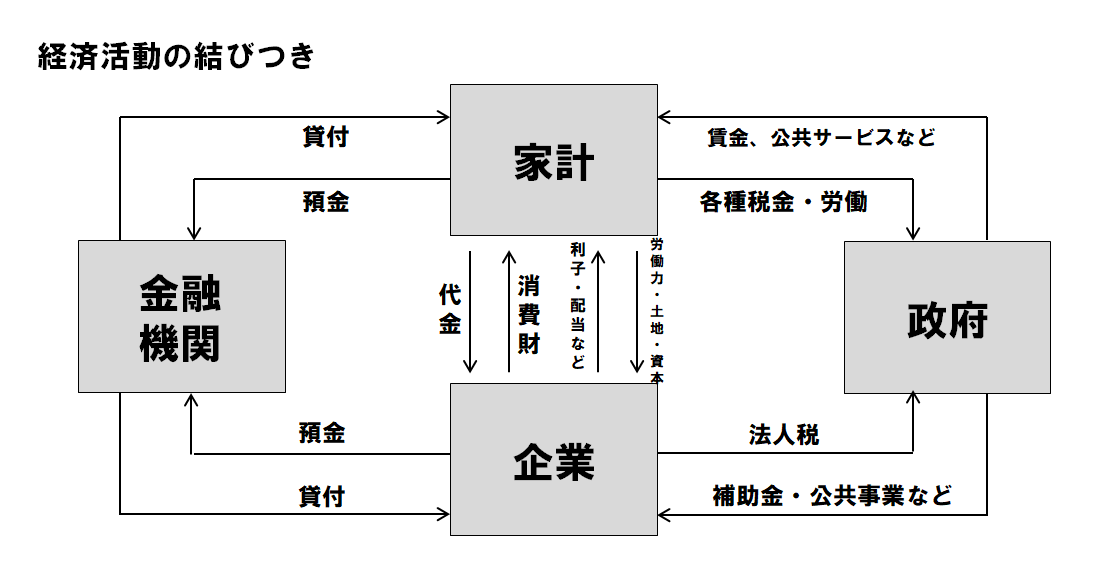
- 消費者主権…消費者が自分の意思と判断によって商品を購入することです。
- 消費生活と契約…個人の意思でだれと、どのような内容でも自由に契約を結ぶことができます。契約自由の原則です。
消費者の権利
1962年、アメリカのケネディ大統領が消費者の4つの権利を明確化しています。
- 安全を求める権利
- 知らされる権利
- 選択する権利
- 意見を反映させる権利
消費者基本法
消費者の利益を守る法律で、昭和43年からの法律。消費者と事業者との間の情報の質や量、交渉力などの格差にかんがみ、消費者の利益の擁護と増進について、消費者の権利の尊重と自立の支援などの基本理念としています。
2004年規制緩和の進展や情報技術の発達で消費者を取り巻く環境が大きく変わってきたことをうけて抜本的な改正が行なわれ,消費者保護基本法から消費者基本法に名称変更されています。
製造物責任法(PL法)
消費者が商品の欠陥により被害を受けた場合、生産者の過失を証明しなくても救済を受けられるようにした法律。
例えば、製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものです。責任を追求できる者としては、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できます。
クーリング・オフ
訪問販売・キャッチセールスなどで商品を購入した後、一定期間内であれば契約を解除できる制度。不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対して、クーリング・オフ制度が設けられました。
具体的には、「訪問販売」と「電話勧誘販売」です。なお、家庭への訪問販売だけでなく、「路上などで声をかけて営業所などへ連れていき契約を勧めるキャッチセールス」と「電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出して契約を勧めるアポイントメントセールス」も法律的には「訪問販売」に区分されます。
対策問題 【定期テスト対策問題】私たちの消費生活


コメント