確率の出題パターンとその解き方です。確率は、入試では、ほぼ100%出題されます。都道府県によっては、大問1題を確率で出題されるなど、得点のウエイトが高いところもあるくらい重要は単元の1つですので、しっかり学習していきましょう。確率の出題は、大きく「さいころ」「コイン」「玉」「くじ」「カード」と分けられます。それでは、確率の出題パターンとその解き方をみていきましょう。
確率の出題パターン
| パターン | 解き方 |
|---|---|
| さいころ | 樹形図でも解けるが、「表」がおすすめ |
| コイン | 樹形図。場合の数は、2個のとき、4。3個のとき、8のように、2個のとき、場合の数は、2nとなることを覚えておこう。 |
| 玉 | 樹形図。表し方は、赤1、赤2などとするより、それぞれをa,b,c,dとアルファべットにするといいでしょう。 |
| くじ | 玉と同じです。 |
| カード | 樹形図を利用しますが、問題に合わせてその形は、同数樹形図と減数樹形図とがある。ポイントは、「同時にひくのか。」「引いたものを一度戻すのか。」を読み取ること。 |
場合の数と確率
- 場合の数…起こりうる場合が、すべてでn通りのときのように、起こりうるすべての数を場合の数といいます。
- 確率…あることがらの起こることが期待される程度を表す数を、そのことがらを起こる確率といいます。
同様に確からしい
さいころの目の出かたは、1から6までの6通りあり、どの目が出ることも同じ程度に期待されます。このようなとk、どの目が出ることも同様に確からしいといいます。
<例>
1つのさいころを投げるとき、出る目は1~6の全部で6通り。そのうち、1の目が出る場合は、1通り。1の出る目が出る確率は、1/6となります。
1つのさいころを投げるとき、出る目は1~6の全部で6通り。そのうち、1の目が出る場合は、1通り。1の出る目が出る確率は、1/6となります。
確率の求め方
起こる場合が全部でn通りあり、そのどれが起こることも同様に確からしいとする。そのうち、ことがらAの起こる場合がa通りあるとき、ことがAが起こる確率はP=a/n(0≦p≦1)
- かならず起こることがらの確率は1
- けっして起こらないことがらの確率は0
和の法則
二つの事柄A、Bがあって、おのおののおこり方がそれぞれm、n通りで、それらがともにおこることがなければ、AかBがおこる場合の数はm+n通りだけある。
積の法則
二つの事柄A、Bがあって、Aのおこり方m通りのおのおのに対してBのおこり方がn通りずつあれば、AとBがこの順序でおこる場合の数はm×n通りになる。
【練習問題】確率
【問1】次の問いに答えなさい。
- A,B,C,Dの4人がリレーで走ります。1番最初にBかCが走るとすると、走る順番は何通りありますか?
- 1,2,3,4と書かれた4枚のカードがあります。このカードのうち。3枚を並べてできる3けたの整数は、全部で何個ですか。
- バレーボールの試合で、A,B,C,Dの4チームがそれぞれ1回ずつ対戦するときの試合数を求めなさい。
- 1つのさいこを投げるとき、2つの目が出る確率を求めなさい。
- 赤玉1個、白玉3個、青玉4個がはいっている袋から白玉を1個取り出すときの確率を求めなさい。
- 赤玉だけが8個はいっている袋から玉を1個取り出すとき赤玉が出る確率を求めなさい。
- ジョーカーを除く1組52枚のトランプをよくきって、そこから1枚をひくとき、ハートの札が出る確率を求めなさい。
- 1から20までの数字が1つずつ書かれた20枚のカードがあります。このカードをよくきって、そこから1枚をひくとき、カードに書かれている12以上の確率を求めなさい。
【問2】
- 2個のサイコロa,b を同時に投げるとき、出る目の数が同じになる確率を求めよ。
- 3枚の硬貨を同時に投げるとき、3枚とも表になる確率を求めよ。
- 6本中に当たりが3本入っているくじがある。このくじをまずAが引いて次にBが引くとき、AもBも当たる確率を求めなさい。
- 1から4までの4つの数字が書かれたカードがそれぞれ1枚ずつある。このうち2枚を取り出して、2けたの数を作るとき2けたの数が3の倍数になる確率を求めよ。
- 2枚の同じコインを同時に投げるとき、少なくとも1枚は表が出る確率を求めよ。
- 3枚の同じコインA,B、Cを同時に投げるとき、少なくとも1枚は表になる確率を求めよ。
- 1~4までの数字をかいたカードが1枚ずつある。このカードをよく切って1枚ずつ2枚取り出して、取り出した順番に左から並べて、2ケタの整数をつくる。2ケタの整数が偶数となる確率を求めよ。
【解答】確率
【問1】
- 12通り
- 24個
- 6試合
- 1/6
- 3/8
- 1
- 1/4
- 9/20
【問2】
- 1/6
- 1/8
- 1/5
- 1/3
- 3/4
- 7/8
- 1/2
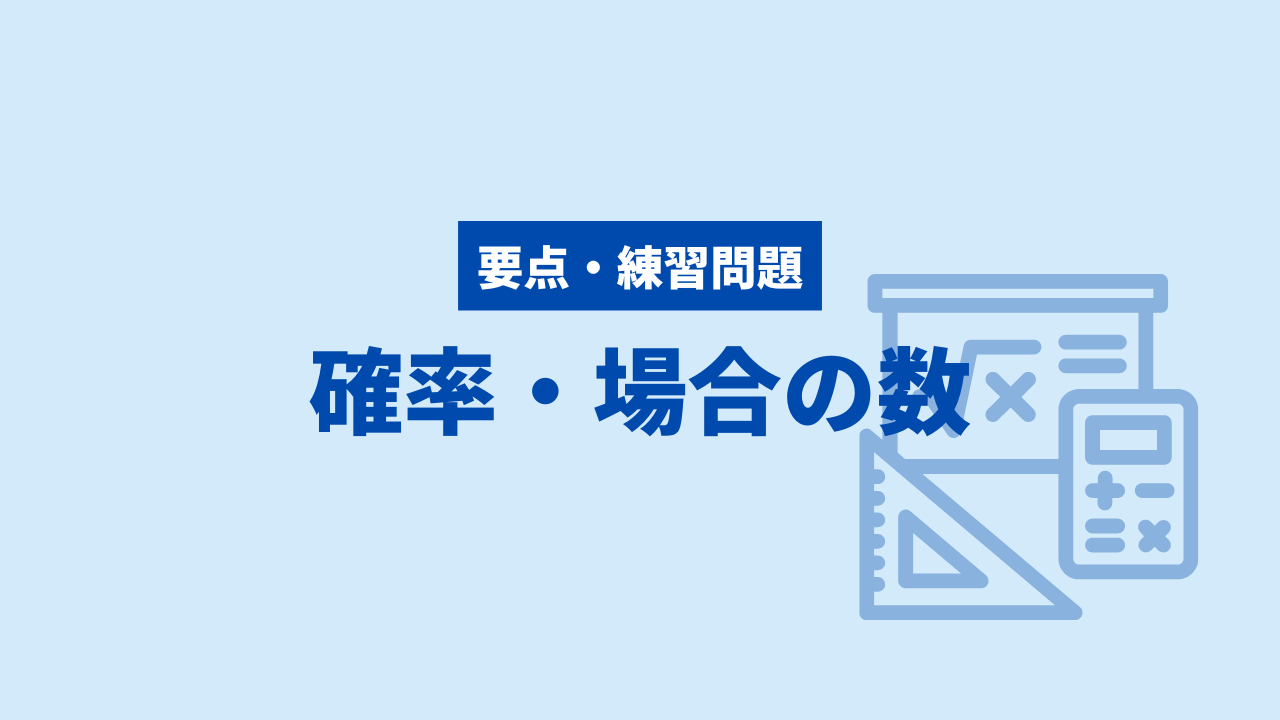

コメント