【確認問題】飛鳥時代一問一答
次の問いに答えよ。
- 590年代に初の女帝(女性の天皇)として政治を行った天皇は誰か。
- 6世紀の末に中国を統一したのはどこか。
- 隋の後に中国を統一したのはどこか。
- 推古天皇を助けて政権をにぎったのはだれか。
- 聖徳太子は何という位についたか。
- 聖徳太子は家がらではなく才能によって役人を採用する制度を作ったが何というか。
- 聖徳太子は役人の心得を示したが何というか。
- 聖徳太子が保護した宗教は何か。
- 聖徳太子が中国に送った使いを何というか。
- 遣隋使の代表的人物はだれか。
- 聖徳太子が建てた現存する世界最古の木造建築である寺は何という寺か。
- 645年に起った中央集権国家を作るための変革を何というか。
- 大化改新でほろぼされた豪族は何氏か。
- 大化改新の中心人物で後に藤原氏となったのは誰か。
- 大化改新の中心人物で後に天皇となったのは誰か。
- 中大兄皇子は何天皇になったか。
- 天智天皇の死後、あとつぎをめぐって起った争いを何というか。
- 壬申の乱に勝った大海人皇子は何天皇になったか。
- 645年に蘇我氏を滅ぼし、新しい政治を始めたことをなんというか。
- 白村江の戦いのち、九州の防護におくられた者をなんと呼ぶか。
【解答】飛鳥時代一問一答
- 推古天皇
- 隋
- 唐
- 聖德太子
- 摂政
- 冠位十二階
- 十七条憲法
- 仏教
- 遣隋使
- 小野妹子
- 法隆寺
- 大化の改新
- 蘇我氏
- 中臣鐮足
- 中大兄皇子
- 天智天皇
- 壬申の乱
- 天武天皇
- 大化の改新
- 防人
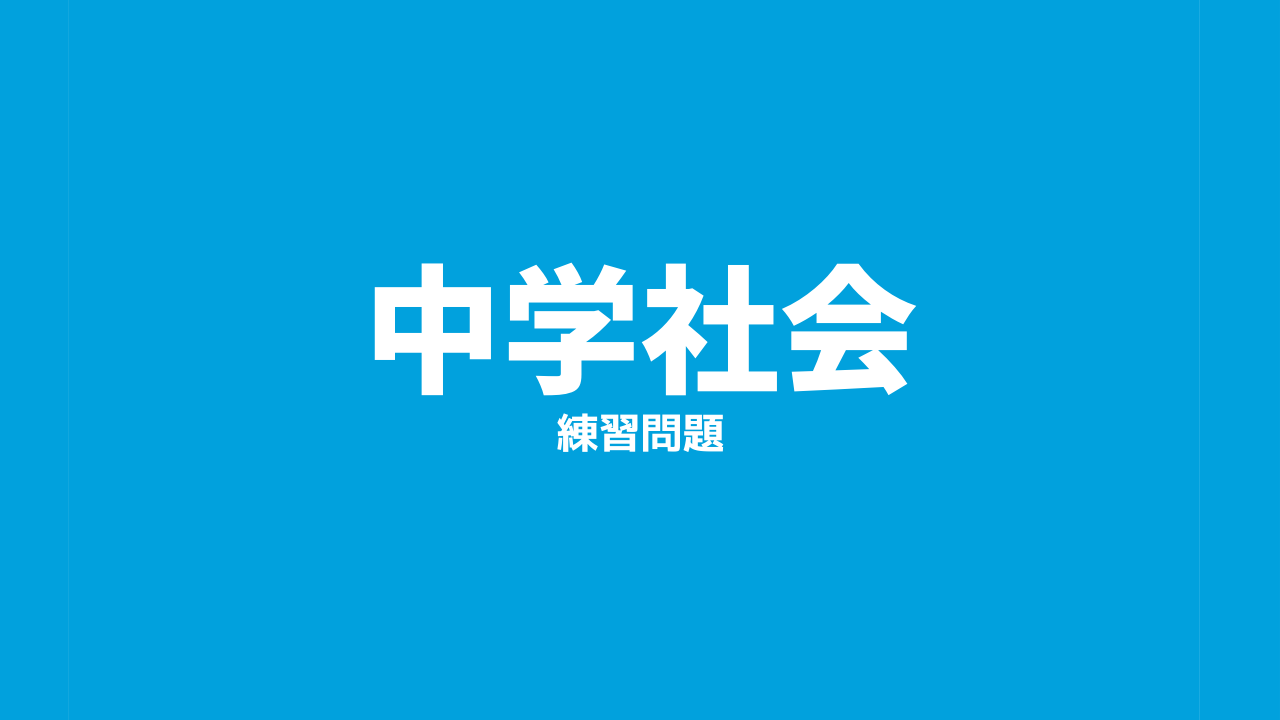

コメント