中学歴史の邪馬台国から古墳時代まで学習します。稲作が始まり貧富の差が生じた社会で、邪馬台国という政治連合国ができ、その後、大和政権が誕生するところまで学習します。この時期は大規模な古墳がつくられた時期でもあります。
➊邪馬台国は倭に3世紀ごろ存在したとされる国。中国の「魏志」倭人伝に書かれている。
➋「宋書」倭国伝には古墳時代の倭のようすが記されている。ちなみに、「漢書」地理誌に記されているののは、紀元前1世紀ごろの倭のようす。
➌大和政権が広がったころに、王や豪族の墓として古墳がつくられた。
古墳時代の要点

入試やテストに出る貝塚・遺跡・古墳の位置
3世紀~4世紀に、近畿地方から瀬戸内海沿岸の各地に豪族たちの大きな墓(古墳)がつくられ始めます。古墳の形や大きさはさまざまですが、4世紀に大和(奈良県)でつくられ始めた前方後円墳は大きなものが多いです。古墳がさかんにつくられた4世紀~6世紀ころまでを古墳時代と呼びます。
国士の統一
5世紀になると、九州地方南部から東北地方南部までの各地に、前方後円墳がつくられるようになりました。特に大阪平野を占める河内(大阪府)には、大仙古墳(大山古墳仁徳陵古墳)などの巨大な前方後円墳がつくられました。また、筑紫(福岡県)・吉備(岡山県)・出雲(島根県)・毛野(関東平野北部)でも、大きな前方後円墳が築かれています。
大和朝廷が河内を根拠地に勢いを強め、各地の豪族をしたがえ国土の統一を進めたと考えられています。大和朝廷の中心となった豪族のかしらは、大王(のちの天皇)とよばれます。5世紀末の稲荷山古墳の鉄剣はそのころ大王が関東地方をも支配したことを示す。
Q:熊本県江田船山古墳と埼玉県稲荷山古墳から、大王(天皇)の名が刻まれた鉄剣が出土したことから、どんなことがわかるか?
A:大和政権の支配が、九州北部から関東地方まで広がっていたことがわかる。
倭の五王
5世紀の終わりごろに書かれた中国の歴史書、『宋書』倭国伝には、5世紀に倭(日本)の5人の大王がつぎつぎに使者を中国に送ったことが記されている。5人目の武という大王は、中国の皇帝に出した手紙に、自分の祖先が武力で国土の統一を進めたことを書いている。これを倭王武の上表文という。この倭王の武は、ワカタケル大王(雄略天皇) のことだろうと考えられている。
古墳時代の文化
- 前方後円墳…大仙古墳のような、方形の前部と円形の後部からなる代表的な古墳の形
- はにわ…古墳のまわりや頂上に並べられた素焼きの土製品
- 須恵器…渡来人によって伝えられたかたい質の土器
渡来人
渡来人とは、中国や朝鮮から進んだ技術や学問を伝えた人々のことをいいます。渡来人により、漢字や仏教、須恵器、養蚕、造船などの技術が伝わりました。
代表的な渡来人として、王仁と弓月と阿知です。中でも、西文氏の祖となった王仁は、論語・千字文を伝えたとされ、弓月君は秦(はた)氏の祖で、そのまま機織り・養蚕を伝えたとされます。
宗教の伝来
儒教と仏教も相次いで伝わってきます。伝えたのは「百済」の「聖明王」から「欽明天皇」へとされ、聖徳太子の伝記『上宮聖徳法王帝説』のなかでは、538年に伝わったとなっています。
朝鮮との関係
このころの朝鮮半島には、北部に高句麗(こうくり)、東部に新羅(しらぎ)、西部に百済(くだら)があり、南部の小国が分立していた加羅(から)(任那みまな)に大和政権は勢力を伸ばしていました。大和政権はこの地で、鉄資源を得ていたというわけです。
このころ、大和政権が中国の王朝に使いを送った理由は、朝鮮半島での優位性を確保したかったからなんですね。
一問一答 【中学歴史】古墳時代の一問一答
対策問題 【定期テスト対策問題】古墳時代
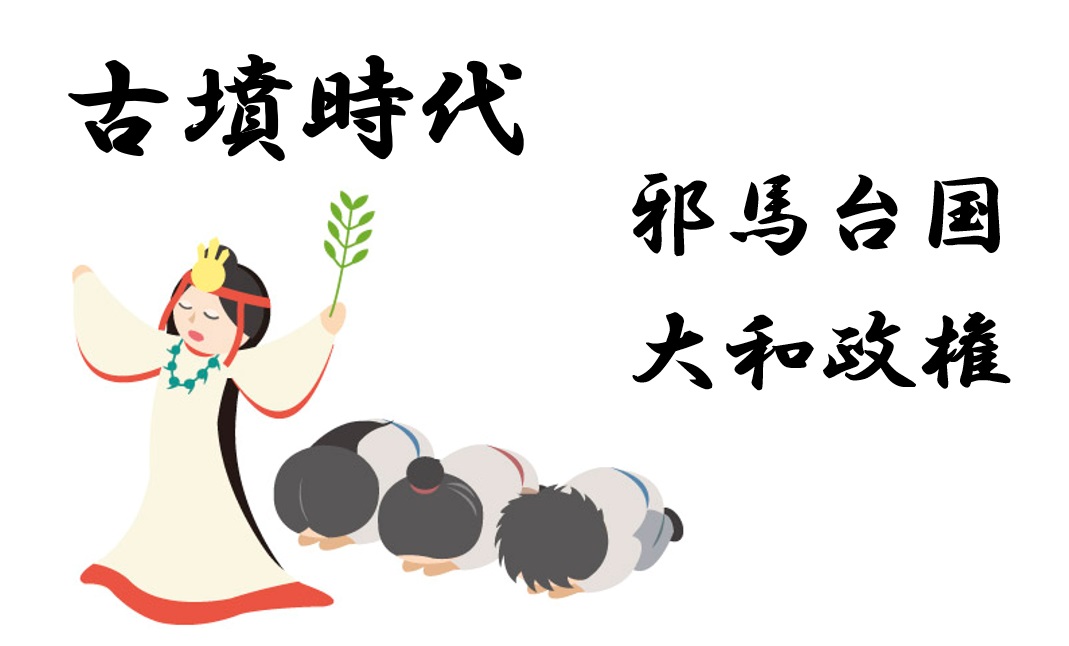

コメント