中学1年理科。今日は「顕微鏡」について学習していきます。身近な生物を拡大して観察できる顕微鏡の名称や使い方をマスターしましょう。
顕微鏡
顕微鏡は、大きく分けると拡大の能力が大きい普通の顕微鏡と、拡大能力は低いものの、立体的に物体を観察できる双眼実体顕微鏡があります。それぞれの各部の名称もよく聞かれるので、最低限下の図の名称は覚えておきましょう。
顕微鏡の各部の名称
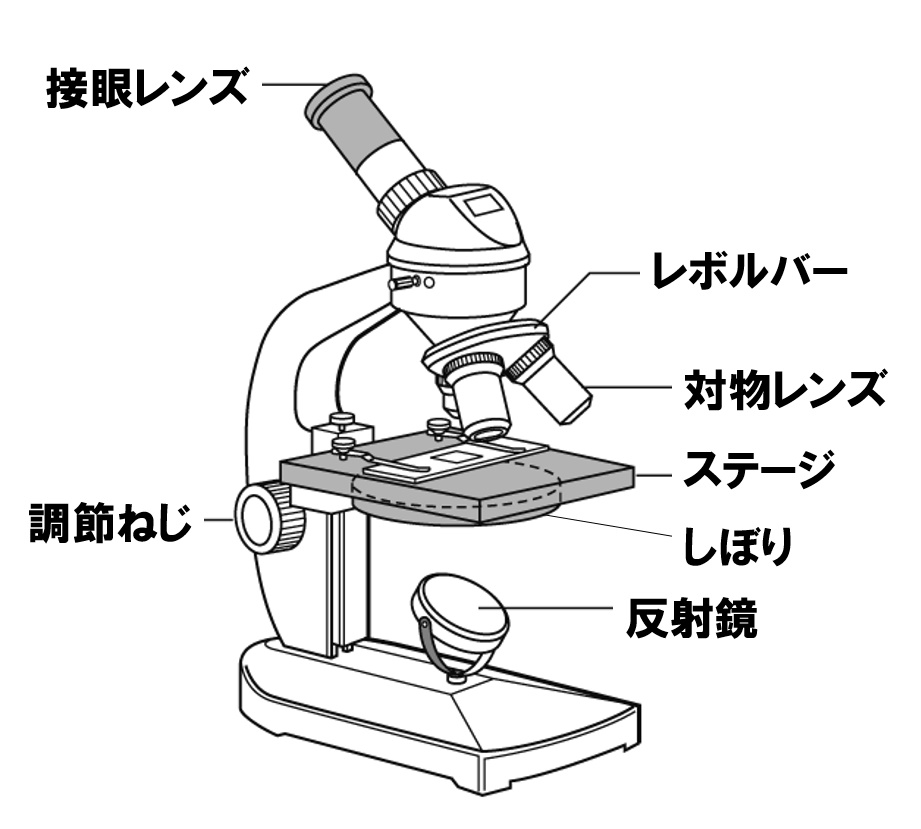
- 接眼レンズ…目に接しているレンズ。短い方が倍率が高い。
- 対物レンズ…観察物に対しているレンズ。長い方が倍率が高い。
- ステージ…プレパラートをのせる台。クリップがついている。
- 反射鏡…光を反射する鏡。平面鏡と凹面鏡がある。
- レボルバー…3つの対物レンズを装着でき、回転させ倍率を変えることができる。
- しぼり…反射鏡からの光の量を調節するダイヤル。絞ると光が少なくなる。
- 調節ねじ…ステージや鏡筒を上下させ、ピントを合わせるはたらきがある。
双眼実体顕微鏡の各部の名称
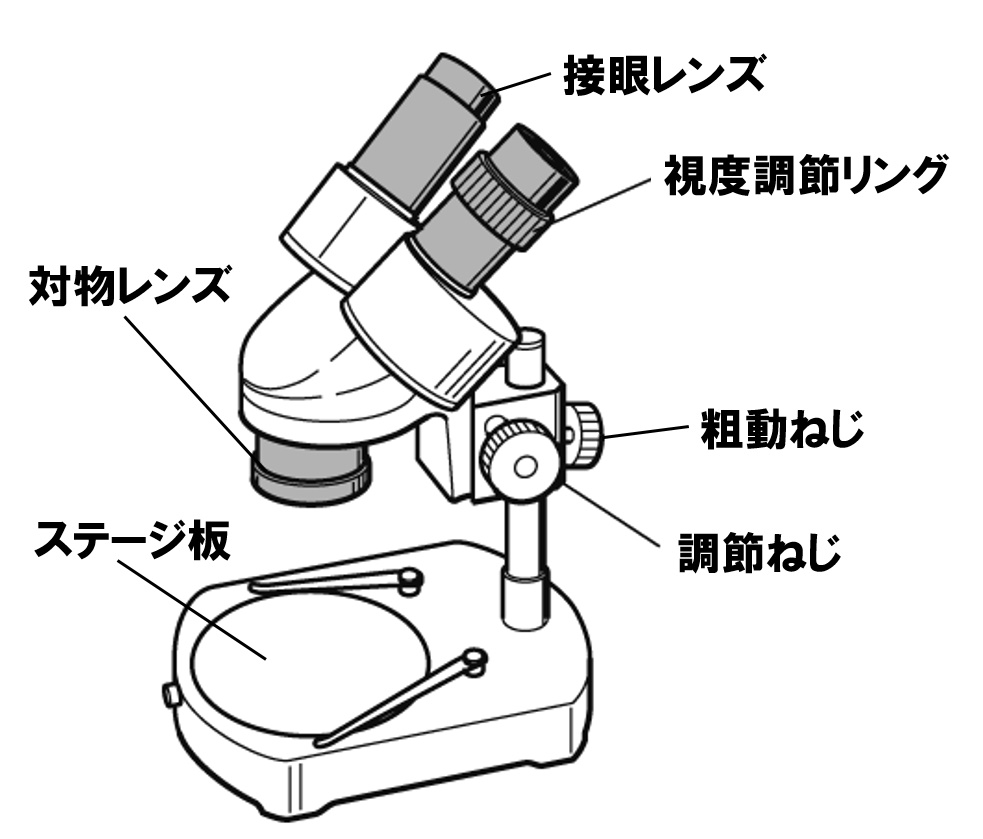
- 接眼レンズ…目に接しているレンズ。短い方が倍率が高い。
- 対物レンズ…観察物に対しているレンズ。長い方が倍率が高い。
- ステージ板…白と黒があり、ひっくり返すと色を変えることができる。
- 粗動ねじ…顕微鏡上部の固定をはずし、大雑把にピントを合わせる。
- 調節ねじ(微動ねじ)…細かなピント調節に使用する。
- 視度調節リング…さらに細かなピント調節に使用する。
顕微鏡の操作手順
顕微鏡の問題では、顕微鏡で物体を観察するまでの操作手順がよく出題されます。次の手順で操作します。理由まで聞かれるので、記述できるようにしておきましょう。
- 明るく直射日光が当たらない水平な台の上で使用する。
〈理由〉目を痛める恐れがあるから。 - 顕微鏡にレンズを、接眼レンズ→対物レンズの順に取り付ける。
〈理由〉鏡筒内に空気中のほこりが入らないようにするため。 - 反射鏡としぼりを使って明るさを調節する。
- ステージにプレパラートをのせる。
- 横から見ながら、対物レンズとプレパラートを近づける。
- 接眼レンズをのぞき、対物レンズとプレパラートを遠ざけながらピントを合わせる。
〈理由〉対物レンズとプレパラートが接触するのを防ぐため。 - 観察物を視野の中央に動かし、レボルバーを回し高倍率にする。
〈理由〉最初から高倍率にすると、視野が狭く観察物が見つからないから。
特に、3と4の順番を間違える生徒が多いです。ステージに何も乗せていない状態で明るさ調節をし、その後にプレパラートをステージにのせます。
低倍率と高倍率
顕微鏡で物体を観察する場合、まずは低倍率で観察し、観察物を視野の中央にもってきてレボルバーを回し高倍率に変えます。このときの視野の変化がよく聞かれます。
| 低倍率 | 高倍率 | |
| 視野の広さ | 広い | せまい |
| 視野の明るさ | 明るい | 暗い |
| 対物レンズとプレパラートの距離 | 長い | 短い |
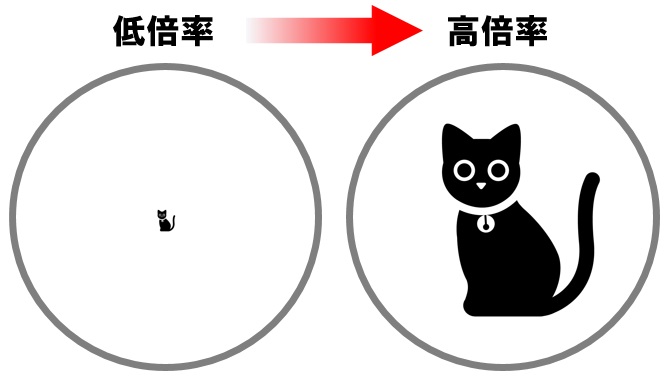
以上、顕微鏡のポイントでした。
対策問題 【定期テスト対策問題】顕微鏡の使い方とルーペの使い方


コメント