【中学理科】偏差値60突破のための理科実践問題|合格を確実に!です。
一般的に、偏差値60はかなり高いレベルの能力や成績を持っていることを示しています。その分布を考えると、標準偏差にもよりますが、偏差値60は上位15~20%程度の位置に相当します。つまり、100人受験したあるテストで偏差値60を取った場合、その試験を受けた人々の中で上位15~20位の成績を収めたことになります。
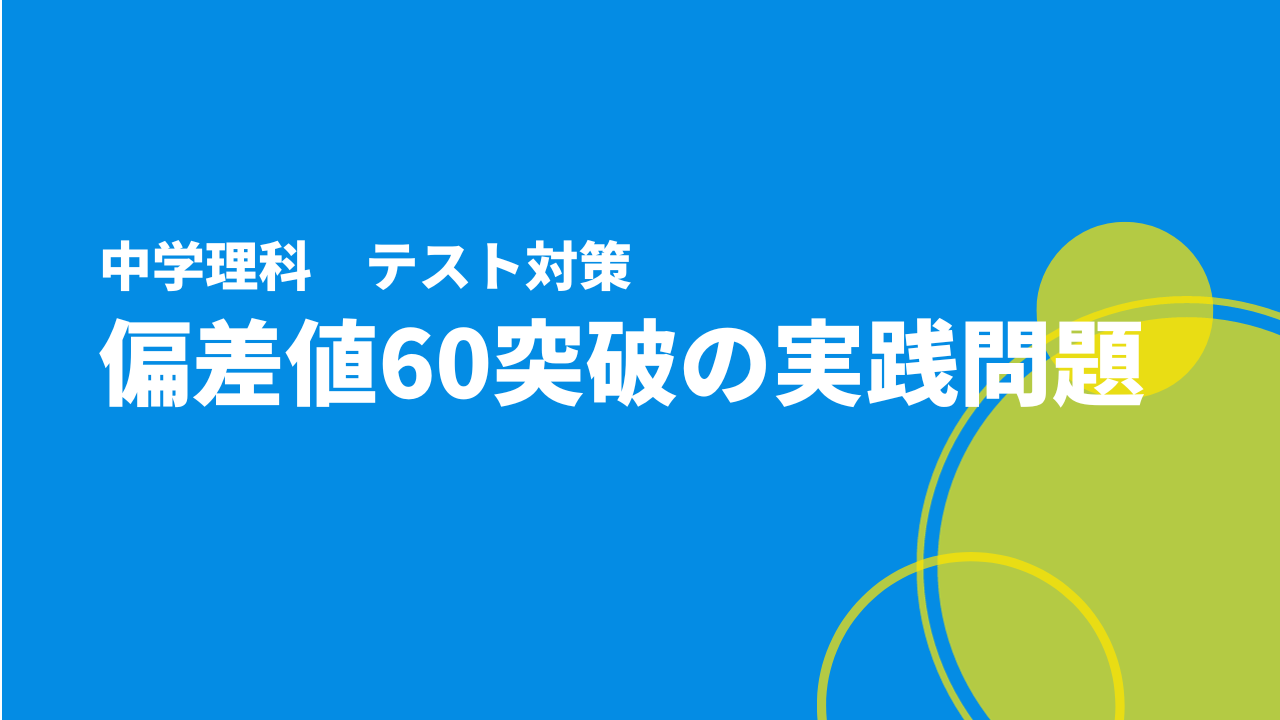 中3理科
中3理科【中学理科】偏差値60突破のための理科実践問題|合格を確実に!です。
一般的に、偏差値60はかなり高いレベルの能力や成績を持っていることを示しています。その分布を考えると、標準偏差にもよりますが、偏差値60は上位15~20%程度の位置に相当します。つまり、100人受験したあるテストで偏差値60を取った場合、その試験を受けた人々の中で上位15~20位の成績を収めたことになります。
コメント